みなさん、一生懸命コードを覚えていますか?
ダイアグラムを見てポジションを覚えて、または音名とコードの成り立ちを覚えて。
なるほど、コードってそういうことだったのかー、と。
そういうルールなのかー、と。
思っているかもしれません。
確かに、ルールは存在しますが
絶対にこれ、という正解はありません。
曲のコードの順番や、コード自体の押さえかた・構成音(響き)もそうです。
なぜなら、コードは解釈だからです。
どういうことか?
見ていきましょう。
コードとは
そもそもコードとは何か。日本語では「和音」といいますが。
コードとは、少なくとも3つの異なる音(音名)を重ねたものです。
なぜ3つなのかというと、コードには機能・役割があり
その機能・役割を決定づけるのに3つは必要だからです。
基本的な音の重ね方を知りたい人はこちらを参考に。
「コードの成り立ち ~意味から考える~」
「コードの成り立ち その2」
「コードの成り立ち その3」
「コードの成り立ち その4」
「コードの成り立ち その5」
なぜ解釈か
厄介なことに、コードは展開形やオンコード、テンション、オミット(省略)など
元のコードの形どおりには弾かないことが多々あります。
オンコードがわからない人はこちら(オンコードの役割)
展開形はコードネーム自体はかわりませんが、音の順番がかわるため響きが変わります。
さらに代理コードや裏コードなど、あるコードの変わりに使えるというコードもありますね。
そして、コードは元々は主旋律(歌や、楽器の主なメロディ)に対するハーモニーとして拡大されたものなので
「主旋律ありきで考える」とするならば
主旋律が動く度にコードネームがめまぐるしく変わる、ということになります。
まぁ、それは現実的ではないよね(笑)
でも、主旋律がコードトーン以外の音でロングトーン(長く伸ばす)を出しているとしたら
それはもはやコードの一部としても良いのでは? ともなります。
後述しますが、オミットしていると考えるなら
どこをどう切り取った(オミットした)か、でいくらでもパターンが思いつきます。
また、ピアノ曲とかなら割とシンプルにコードは拾うことができます。
必ずと言っていいほど左手でコードのルート(コードの基盤となる一番低い音)を出しているので。
バンドものになると、
ベースを聞いて、ギターを聞いて、鍵盤はこんな感じだしー、という具合に
様々な楽器の音を拾う必要があります。
全ての楽器が同じ音を出してくれているわけではないので、
頭の中でそれぞれの音を足しあわせてコードを構築するんです。
こういった点から、コードは解釈と言えます。
コードの定義が変わるという意味ではなく、
どのコードネームをつけるのかは音を拾う人による、という意味です。

具体例
具体例を見ていきましょう。
「ドミソ」という音の並びがあるとします。
これは一般的にはCコードと解釈する人が多いでしょう。
ところがAm7(ラドミソ)のルートのオミット(省略)とも考えられるわけです。
さらには、Dm7(9,13) (レファラドミソ)の1・3・5度オミットともとれます。
さらにひねくれた解釈をすると、C△7(ドミソシ)の7度オミットとも言えます。
さすがに、ここまで考える人はいないか(笑)
また、オンコードだと
Bm7(シレファラ)なのか、D/B(シレファラ)なのか。
どちらも同じ音名で構成されていますよね。
ギターは出せる音が最大で6個なのと、基本的には左手でしか押さえないため
どこかしらの音を最初からオミットしていることが多いんですが。
「オミットしているかも」と想像を膨らますだけで、パターンが無限に広がります。
問題点
コードは解釈、ということになると
ある問題が出てきます。
それは
本やサイトによって、書いてあるコードが違う
ということです。
お気に入りの本やサイトなど、一つの情報源にとらわれすぎると
コードの知識や幅が広がりません。
まぁ、あまり理解していないうちは混乱するだけなので、一つに絞ったほうが良いですが。
たまに「さすがにそのコードじゃないやろ」ってコードが書いてあるものもあります。
このへんは大人の事情というか。
結局、本やサイトを作っている企業があるわけで。その企業も誰かに報酬を支払ってコードを拾ってもらっているわけで。
一人の人にコードを拾ってもらうのと、
複数人にコードを拾ってもらって解釈のズレがないか確認するのとでは、
支払う報酬が変わってきますよね。
そういうことです(笑)
バンドスコアなども同じです。
楽器の数だけ担当者に依頼する、または複数の楽器のことを高いレベルで理解している一人に依頼する、ってのと
ドラマーだけどギターのことも少しわかります、って人に依頼するのと
どちらの方がスコアとしての完成度が高いですか?
どちらの方が報酬が安くて済みますか?
ってことです。
解決法
コードは解釈。
本やサイトもあてにならない。
では、どうするの?
自分で覚えましょう。
コードの仕組み・成り立ちをです。
そして耳コピも必要になります。
耳コピが苦手な人は「耳コピ・音感・落とし穴」の記事を参考に。
どうしても他の情報に頼りたいというなら
複数の情報を確認しましょう。
複数の本、複数のサイト。そして、比較します。
一方にDと書いてあり、もう一方にD7と書いてあるなら
なんとなく「D系」のコードなんだろうな〜と。
もう一方にD系でない全く違うコードが書いてあるなら
そのときは勉強のチャンスです。
なぜこの解釈なんだろう、と。
ただ単に間違って書いてあるだけかもしれませんが。
なぜ間違ったのだろう、と考えるのも勉強です。
色々知識がついてくると、間違った理由も見えてくるようになります。
あてにならない情報を元に、違っているかもしれないコードで弾いた気になるか
自分の知識と耳で確かめて、納得したうえでしっかり弾くか
どちらを選ぶかはあなた次第です★


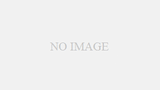

コメント